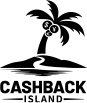米6月PMIはわずかに減速、インフレ懸念は依然根強い
6月の米購買担当者景気指数速報
米S&Pグローバルが2025年6月23日に公表した6月の米国購買担当者景気指数(PMI)速報値は、総合で52.8と、前月の53.0から小幅に低下した。依然として景気拡大を示す50の水準を上回ってはいるが、トランプ米大統領による包括的な関税導入などの影響で物価の上昇圧力が強まっており、今後のインフレ加速への懸念が浮き彫りになっている。
Cashback Islandでは、「6月のFRB政策金利」「米国5月小売売上高」「アメリカ5月の消費者物価指数」などの経済指標を更新している。詳細については、ぜひ「Cashback Island マーケット情報」セクションをご覧ください。
製造業PMIは市場予想上回るも、企業心理には慎重さも
6月の製造業PMIは52.0と、市場予想の51.0をやや上回る結果となった。また、サービス業PMIは53.1と、前月の53.7からは減速しつつも依然堅調な水準を維持している。
S&Pグローバルは、製造業の一部で楽観的な見方が若干広がっていると指摘した。その背景には、「保護主義的政策による国内需要への期待」があるという。一方で、トランプ米大統領就任以前と比べ、企業全体の先行き見通しは慎重な傾向が続いているとの見方も示された。
物価指標にインフレ圧力の強まりが鮮明に
物価関連の指標では、インフレ圧力の強まりが顕著に現れている。製造業の投入価格指数は70.0と、前月の64.6から大幅に上昇した。これは2022年7月以来の高水準となった。投入価格の上昇要因として、約3分の2の製造業者が「トランプ政権の関税措置」を挙げている。
一方、サービス業の投入価格指数は高止まり傾向が続いているが、前月に比べるとやや上昇ペースは鈍化した。資金調達コストの上昇や輸送費の増加も影響しているとされる。
製造業の販売価格指数も59.7から64.5へと急上昇し、こちらも22年7月以来の高水準に達した。こうした動向は、インフレが今後さらに高まるリスクを市場に示唆している。
受注増で雇用指数は回復傾向
雇用指数は改善したものの、その主因は製造業の回復にあるとみられる。特に一部の工場では、国内需要の高まりや在庫積み増しの影響により注文が増加し、受注残が発生している。これが新たな雇用の創出につながった形だ。ただし、雇用の拡大が今後も持続するかどうかについては、不透明感が残っている。
コスト圧力の持続や需要鈍化への懸念
6月の統計では、関税政策が製造業・サービス業双方にコスト面で大きな影響を及ぼしていることが改めて浮き彫りとなった。特に製造業では、仕入れ価格や販売価格の上昇に加え、在庫の積み増しも続いており、短期的な成長支援要因となる一方で、中長期的には企業のコスト圧力や需要鈍化への警戒が必要とされる。
ウィリアムソン氏は「こうした押し上げ効果は今後数カ月で徐々に和らいでいく可能性が高い」と分析した。米経済は一時的な需要拡大の反動や、インフレ再加速のリスクといった新たな課題に直面する局面に入っていると見られる。
今後の見通し
今回のPMIデータは、トランプ政権が導入した包括的な関税措置がサプライチェーンと価格形成メカニズムに既に影響を及ぼし始めていることを明確に示しており、今夏から秋にかけての米国経済において、インフレ動向と企業収益のバランスが重要な監視項目となっていくと考えられる。
今後の注目点としては、6月のPMI確報値と、6月の雇用統計が挙げられる。特に、賃金上昇圧力と価格転嫁動向の詳細なデータが、FRBの金融政策判断に影響を与える可能性が高い。現在の製造業主導のインフレ圧力がサービス業にまで波及するかどうかが、今後の米国経済の鍵を握るとみられる。
よくある質問
Q1.購買担当者景気指数(PMI)とは?
A1.購買担当者景気指数(PMI)とは、企業の購買担当者を対象に実施される景気動向調査の結果を基に算出される指標だ。主に製造業とサービス業の経済活動を測定し、景気の先行指標として活用される。
PMIの結果が市場予想を上回ると、景気の拡大が期待され株価や通貨(特にドルなど)が上昇しやすい。一方、予想を下回ると景気減速懸念から売り圧力がかかることが多い。
Q2.PMIの速報値と確報値の違いは?
A2.PMIには速報値と確報値の2段階の発表がある。速報値は月末近くに発表される予備データで、市場への影響が大きい一方、確報値は月初に発表される最終的な調査結果で、精度が高いとされる。
Q3.今回のサービス業PMIが製造業PMIを上回っているのはなぜか?
A3.サービス業は国内需要に依存する割合が高く、現在の米国経済では個人消費が堅調に推移しているためだ。一方で製造業は貿易摩擦や為替変動の影響を受けやすく、特に輸出依存度の高い企業では景況感が抑制される傾向がある。ただし、両者の差は近年縮小傾向にあり、今回のデータでは僅差となっている。